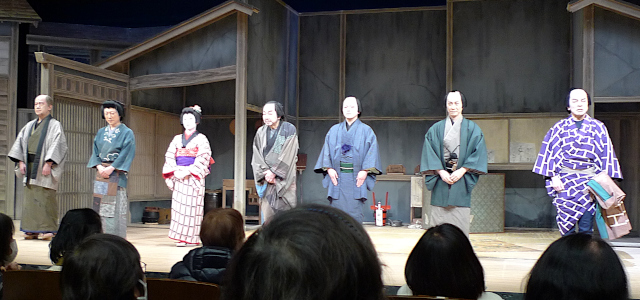
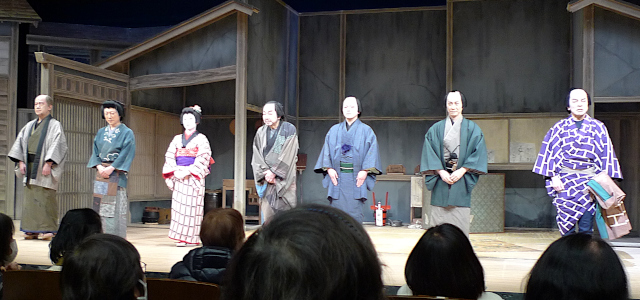
■ 文七元結は2回目になりますが、人情噺はとっても感動的で、日本人ならではの内容で、とても良かったです。是非また、市民劇場で取り入れてほしいです。
■ 久し振りに前進座の人情噺を観た気がします。歌舞伎の伝統的な決まりや所作を解りやすく説明していただき、一層観る楽しさや面白みを味わうことが出来ました。とても人情に溢れた暖かいものをしみじみ感じました。
■ 最初に「歌舞伎入門講座」があったので、舞台演出を理解した上で、楽しく観劇できたのが良かった。長兵衛のだらしなく、生活力のなさに、「なんだこの人ダメダメじゃん!」と思っていたけど、タイトルにもある人情、他人への思いやりが見えて、最後は好きになった(笑)。ハッピーエンド、最高 ‼
■
考えれば、たった2日間の出来事。なんとなんと、悲喜こもごもの出来事が起こったもの・・・
そして、雨降って地固まる。一方、禍福門なし唯人の招く所とか。長兵衛夫婦、文七夫婦の行く末も、ちと気がかり。まあ、文七考案の元結(もとゆい)が実際馬鹿売れしたらしいから、善しとしようか。
■ ほっとした気持ちになる舞台でした。場面転換が大変そうで、いい会場(劇場)があればいいのにと思いました。
■ バクチと酒におぼれた主人公が、娘の見受け金として借りた50両もの大金を、身投げしようとしている若い男に惜しげもなく与えるというようなことは、普通では考えられないことですが、江戸っ子の人情噺としては、人気があり面白いのだと思います。楽しいひとときでした。
■
「楽しい歌舞伎」が「文七元結」を観るのに役立った。特に舞台変換の際の拍子木の意味がよくわかり、待っている間の楽しみとなった。
「文七元結」は、人情溢れる話の展開が良かった。せちがらい昨今の中、心がなごやかになった。
■ この度は、バックヤードの見学を体験出来た事、舞台を支える裏方さん達の細やかな心遣いに感動。
■ 前進座は大好きです。歌舞伎講座も楽しいし、「さんしょう太夫」や「芝浜の革財布」などが印象に残っています。今回も、人情物で、江戸の気性そのままに笑いありで十分楽しめました。
■
今回、初めて歌舞伎劇を間近に観ることができて大変良かったです。最初に、歌舞伎のあれこれを分かりやすく説明していただき、なるほど・・、と感銘しました。あと、物語のあらすじを読んでなかったため、自分が想像していたストーリーとはちがい・・?主人公の長兵衛が五十両の金をバクチに使い込み、また元の木阿弥になると思いきや! ハッピーエンドに‼
人は良い事をすると、ハッピーになれるのですね! よかった! よかった!
幸せな気持ちで帰路につきました‼
■
江戸人情噺を存分に楽しませてもらいました。
「楽しい歌舞伎」も楽しく、日本舞踊も華やかで良かったです。
■
新会員の夫婦です。分かり易い人情噺でしたが、舞台に間近の席で、歌舞伎役者の迫力ある演技力や最終のハッピーエンド場面では目頭が熱くなりました。
本番前に、歌舞伎進行のABCが紹介され、理解が深まり、よかったです。
■
人情とはこういうことか…身内にはいい加減なことをして、娘が身を売るほどひどい事をしながらも、他人の不幸は放っておけない。「情けは人の為ならず」という諺があるけれど、しかし長兵衛の行動はそんな諺は全く頭にあらず。ほぼ本能的に全くの他人を救ってしまった。
結果HappyHappy見ていて、心が豊かになるのを感じました。
■
前に観た気がするが、今回も大変面白く、最後まで興味尽きず観させてもらった。まず、人情噺の内容が泣ける。日本人の心に奥深く響くものあり。身投げする程まじめな手代、自分の身売りまで考える親思いのお久、遊び好きのベランメエ左官の長兵衛、しっかり女房のお兼・・・
ふた昔前の日本の縮図のようで、苦労と人の好さに共感と郷愁を覚えた。
次に話の進み具合、成程これぞ歌舞伎と思わせる台詞口調もゆっくり、はっきりで、心にしっかり響いてくる。アメリカ調の陽気さ明るさとは全く違う。
女形扮する女房、吉原の女主人も貫禄十分で、長兵衛への説教も説得力抜群。
また、音曲、擬音太鼓、舞台装置もあざやか、華やかで、さすが伝統芸能、見る目も聴く耳も楽しませてくれた。
■
運営サークルの役得で、17時から劇団員さんとの顔合わせの後、バックステージツアーで舞台裏、楽屋を見せていただいた。お兼さんが着用する着物のメンテナンスが大変らしく、プロの衣装さんの手を借りなければ、舞台は成り立たないということを聞き、舞台づくりにおけるプロの仕事の意識の高さに驚かされた。そして、舞台の方へ進むとそこには引き戸が立てかけてある。その色合いも強い照明が当たることを考慮して塗られたそうだ。そういったことを頭に入れて舞台を観させていただき、よりいっそう楽しんで観ることが出来た。
落語を元に演出された物語であるだけに、セリフのやり取りがテンポよく、場面が数分でがらりと変わるのも、とても計算された演出で長くても短くてもいけない。スピード感もありつつ、熟練された職人技で、幕の裏側でトントンとくぎを打つような音が聞こえ、どんな作業をしているのかな?とワクワクしながら、楽しむことが出来た。笑いあり、涙ありのとても心が温かくなるような舞台だった。
また来年の3月「あかんべえ」で来られるとのこと。今から楽しみにしている。
■
いつもよりお芝居に引き込まれる感じがして、とても良かったです。私には、お話の長さがちょうど良かったのかもしれません。
また前進座さんの舞台を観るのが待ちどおしいです。
■
今回の「文七元結」では、最初に歌舞伎の手や体の使い方仕草さなどの説明があり、体の使い方によっては若い人から老婆まで自在に演じられるのだと知りました。勿論大変な修練をされての事でしょうが。
最前列で観る事が出来たので役者さんの顔の表情や目にまで感情を感じさせられ舞台に夢中にさせられました。身投げをしようとするのを引き止めながらも、他人の命か娘の体を引き替えにしたお金か、究極の選択をする場面に一番心を惹かれました。本当に迫力あり、ちょっとした所で笑いがある楽しい時間をありがとうございました。
■
一言で言うと、「とても楽しめた例会」でした。
わたしも子どもたちも、歌舞伎風演劇に触れるのは人生で初めて。
歌舞伎というと、どこか難しそうな、堅そうなイメージがあり、「小学生の息子には難しいかもしれない…」というのが、観る前の率直な印象でした。
ところが、本編の前に歌舞伎講座で歌舞伎を楽しむためのポイントを楽しく教えてくれ、期待が高まったところで幕を開けた本編は、役者さんたちの演技の巧さ、舞台芸術の美しさ、ストーリーの分かりやすさが相まって、グイグイと魅き込まれてしまうものでした。
もちろん子どもたちも飽きることなく楽しみ、観終わったあとの満足したような顔は今でも忘れられません。今まで知らなかった歌舞伎の世界に、楽しみながら触れることができ、子どもたちにとってもとてもいい「出会い」になったと感じました。
余談ですが、現在放送中のNHKの朝ドラに、池畑慎之介さんが出演しています。
わたしが初めて池畑さんのお芝居を観たのは、高校生の時に市民劇場で演じられた「グッバイ・チャーリー」でした。池畑さんのことなど、「い」の字も知らなかったわたしは、そのパワフルで魅力的な演技に、まるで恋に落ちたように心を奪われました。そして二十数年経った今でも、朝ドラで池畑さんの出演シーンをわくわくしながら見ています。こんな風にドラマを楽しめるのも、高校時代の「出会い」があったからに他なりません。
わたしの子どもたちは、まだ2例会分の舞台しか観ていませんが、これからも市民劇場の例会を通じて、高校時代のわたしのように「決して忘れることのできない出会い(それは俳優に対してでもあり、作品・音響・照明などすべてに対して)」を体験してもらいたいと願っています。そうすることで視野は広がり、人生が豊かになるであろうことを信じてやみません。
よい「出会い」をありがとうございました。
■
徳島ではなかなか味わえない歌舞伎の世界を、笑いあり、涙ありで、楽しく見せていただきました。先に「楽しい歌舞伎」であれこれと歌舞伎の面白さを教えていただいたのが、とても良かったです。
これを機会に、これからも歌舞伎を見に行きたいと思います。
■
古典落語の人情噺をどう演出されるのか、楽しみにしていました。期待以上の面白さ、親子の情の深さ??さすが「前進座」ですね。ハッピーエンドの結末は、安心して観られます。
「鳴門市民劇場」の会員になって数年、会場のシートに座り続けることが苦痛になってきました。楽しく時の流れを忘れて楽しめる例会が続くことを期待します。
■
人の命とお金をテンビンにかけることはできない本質的な違いがある。それをテーマにした作品で、登場人物が全て善人であったので楽しく観ました。本来人間はこのように温かいお互いに相手を思いやる心を持っていると思う。今の時代、このような人情が大事なのではと思った。
楽しい歌舞伎は、歌舞伎素人にはとても楽しく、よかった。
■
楽しい歌舞伎で、初心者の私達にはとても勉強になりました。おかげで文七元結の方もわかりやすく楽しく観ることができました。
それにしても矢之輔さんのスラリとした足に見とれてしまいました(笑)

■
新会員です。初めての歌舞伎、面白かった!!最初に「歌舞伎とは何か?」から始まり、太鼓で自然を表すこと、女形の所作等の説明があり、興味深々で聞き入りました。渡会さんの見栄も良かったです。次の舞台で「ワタライ!」と声を掛けたいのを実は我慢していました(笑)。それから、座席は初見ということで真ん前の特等席に座らせてもらえて、ありがとうございました。玉浦さん(酒屋手代)の色っぽい目と合った気がしてドキドキしていました。とにかく、とても素敵な時間を過ごさせてもらいました。「舞台」って本当に良いですよね。役者さんの息づかいまで感じることができる。
どうぞこれからもよろしくお願いします。
■
演者の方の間の取り方が絶妙でしたね。よく笑い、楽しかったです。
昔ながらの安心感のあるいい話しにほっこり、ほっこり・・・
今日も神様貯金をしようと思いました。本当に困った時に引き出して貰えるように
■
だあれも悪い人はいない(まあ…長兵衛さんの「これまで」は、夫としても父親としても許しがたいところですが、今回の物語は「そこからあと」なので)お話って、ありえないよなあと思っても、他人を信じられなくなったり、殺伐としたことばかりが目に耳に入る今の世の中の私たちには、真冬の寒さの中で飲む1杯のホットミルクのように、じわーっと沁みてくるものだなあと、改めて、思いました。こんな風に、人間だからもちろん失敗も愚行も迷いもあったとしても、少しずつ善意を寄せ合っていたら『奇跡的に「いいこと」が起こる!』という世の中になればいいのにな、と、夢想もしてしまうようなお話でした。
軽く笑いをとるシーンでも、それは卓越した役者さんたちの演技力あってこそ…がよく分かる芝居でした。一見シンプル簡単に見える大道具や衣装も、実は深い趣向をこらした芸術作品であることも(一部は、バックステージツアーで解説を受けた結果)よく分かりました。舞台はまさに総合芸術であることを実感できた作品でした。
歌舞伎はとってもゆったりと時間が流れるので、その鑑賞中は、いつも、贅沢をもらっていると感じます。日々をセカセカと生きている私(たち)にたまには必要な時間かもしれません。
■
ハッピーエンドって素晴らしいなぁと。50両の動きが面白い。行ったり来たり。昔からある話は精錬されてると感じました。
歌舞伎の基本知識も勉強になりました。
■
歌舞伎を見るのは初めてです。
最初に座長から前進座が出来て今年で94周年であるとの説明があり、その後に歌舞伎の基礎知識の話がありました。この話が本番の歌舞伎を見るのに大変役立ちました。
今回の歌舞伎はいわゆる人情もので、歌舞伎初心者の私にも良く理解できました。歌舞伎には女性を使わないので女形が必要だとの説明でしたが、前進座は昔から女性も出演しているとの事でした。
■
今回、自動的に歌舞伎を観るチャンスが与えられたことで、堅苦しいと思っていたイメージがずいぶんと変わりました。
最初に登場された長兵衛さんの姿が面白おかしくて、この人は一体どういう人なのかと興味が湧きました。でも、そんな長兵衛さんが主人公だと思うのですが、題目が「文七元結」……とても不思議です。
日本人が大好き(きっと)なお話しで、とても分かりやすくて面白かったです。夫婦になり、お店を出された文七さんのその後も知りたいところです。
また、「元結」の読み方を知り、ひとつ利口になりました。辞書で意味も調べてみました。なるほど~。
最後に、セットもとても見事で素晴らしいものでした。特に、私のお気に入りは、川の対岸にある家の窓です。まばらに灯った窓の明かりに「風情」を感じました。
■
全体的にとても新鮮で面白かったです。
歌舞伎に関する説明も、歌舞伎をあまり知らない私にはとても勉強になりました。
短い間の舞台転換すごいですね。
第三幕かな?川のほとりの場面の背景の絵がとてもすてきでした。
ストーリーもハッピーエンドで、心もほっこりして、心地良く家路に着くことができました。
■
今回の幕開けの「楽しい歌舞伎」は、前回の前進座の公演時でもお馴染みの演出で、歌舞伎に対する観方等々を手軽に理解するのにとても役立っていると思いました。つまり、このちょっとした演出を施すことで観客を舞台へと引き込み、さらには観客と役者とが一緒になって「見得(みえ)」をやってみたりして、ある意味丁度いい軽いウォーミングアップになっていて、これから始まる主劇への誘いとしてうまく機能していたと改めて思いました。
■
誰でも知っている古典落語の演目をどう解釈して表現してくれるのか。先の人形劇/芝居“死神”では、想像もしない/とんでもない解釈/演出で魅せてくれるのだろう・・。と、大きな期待/“楽しみ”を持っての観劇だったが、期待外れの、まったく平凡な、○○であったが・・。
■
お芝居前の歌舞伎解説がとても面白かったです。一緒に見得を切ったのが楽しかった!声かけが難しかったですねー。
■
前半の歌舞伎についての決まりごとの説明、解りやすく今後も参考になりそうです。
■
■
正直「歌舞伎」は全然わかりませんでしたが、少しわかったような気がしました。おもしろい所を教えてくださいました。考えてみますと、自分の近くにも「歌舞伎」の好きな義理の母がいたことを思い出しました。私が少しでも興味をもっていたらお話が弾んだのにと反省しています。「人情噺」は、昔聞きました。日本人の体に流れていますよね。日本人の根底に流れている助け合いの精神ですね。今も災害時などに発揮されます。素晴らしいです。
■
人情噺 文七元結はよかった。やっぱり自分は日本人だなと…
■
■
人情噺「文七元結」、まさしく江戸落語の真髄を劇にしてる噺でしたねぇ。上方落語に慣れてる自分には、とても新鮮に映りました。松竹新喜劇のような、泣き笑いでは無くスピード感、効果音etc…これが江戸っ子、感なんでしょう。
■
久しぶりの人情噺を観た。私自身、自分は主人公とは大きく違うなーと気付いた。便利とか合理性の方に引かれ決断してしまうから…
一方、今回の主軸を為す舞台が始まって終盤に近付くまでは、正直言ってこれといった大きな盛り上がりも無く、意地悪な言い方をすれば私にとっては今回の観劇は「退屈」の二文字でした。加えて、劇の構成もよくある陳腐なパターンで、事前情報無しで観劇に臨む私でも先が読めるほどで、本劇の展開にはこれといった新鮮味や真新しさは感じられませんでした。しかし、それが終盤になって、心地良い笑いとほんわかとした空気感に包まれて、観る私の心も何だか軽く暖かい気持ちとなってきました。そして、そんな心持ちになっている私の劇を観終わって最初に脳裏に浮かんできたのが「『情けは人の為ならず』とは正しくこのこと」というものでした。
ところで、今回の観劇では歌舞伎という事もあってか、至るところにそれとなく笑いを誘う演出がなされていたのも今回の観劇を楽しめた要因の一つなのかなと思いました。とまぁ、ここでいうところの「笑いを誘う演出」は、私の感覚からすれば「ギャグ」です。ですから、いわゆる「ユーモア」とはちょっと違うんですよね…。それで、舞台で繰り広げられた動きから私は「吉本新喜劇」での色んな役者が持ちネタとして繰り出す「ギャグ」を思い浮かべ、そのギャグと目の前での役者の動きとがリンクしたのです。という事でもないんですが、私も思わず笑ってしまう吉本新喜劇的なギャグ(演技)を取り入れており、言わばミニ吉本新喜劇とも捉えられるかなと思いました。とはいえ、吉本のようなキツ目のギャグ攻勢ではなく、抑え気味ながらも品のあるギャグと私の目には映りました。いうなれば「上品な吉本新喜劇」でしょうかね…。
それでは、視点を変えて今回の観劇を眺めてみたいと思います。主人公の長兵衛が身投げをしようとした奉公人の文七へ、悩みながらも最後には佐野槌の女将から借り受けた五十両もの大金をいとも簡単に手渡した行為ですが、果たして同じ状況下に置かれた際に、この私に出来る行為なのか、帰り道では自問自答を繰り返しながら家路へと車を走らせました。ですが、結局は結論を得ることは出来ず、五十両を人の命を助ける為に無償で譲り渡すことが出来るか否か、自問自答しても「出来る」あるいは「出来ない」の間を行ったり来たりして、私自身がその立場に置かれた際にとる行動としては決めかねる思いでした。とまぁ普通の神経の持ち主であれば、かように強く思い悩むものであろうことは容易に察することが出来ます。ということは、いとも簡単に五十両を手渡した長兵衛という男は、「余程のお人よし」、あるいは不適切な表現かも知れませんが「この上ない大馬鹿者」かのどちらかに相違ないと思った次第です。ですが、どちらにせよ、そんな無償の行為が出来る長兵衛は「義理人情に厚い男」との思いも私の心に浮かび上がりました。
さて、その「義理人情」の観点から私の眺める視点を架空の舞台から現実の世界へと移してみると、そこには何が見え映るのでしょうか?
舞台の上ではこの上ない人情味溢れる人物達で構成されていましたが、そこでふと現代社会での私たちの世間というものにも思いを馳せてみると、私の脳裏に浮かんでくるのは、舞台上のような人情味溢れる世界とは相反する世界なのではないかとの一抹の不安を覚える情景でした。もちろん、個々の日々の生活の中では人情味が皆無というわけではありません。ですが、ニュースや新聞紙上あるいはネット上で見聞きする世間での動向を見るにつけ、何とも言えない人情味の薄い厭世的な感情にならざるを得ないような現実に直面してしまいます。例えば、いわゆるSNS上での誹謗中傷、最近では女性の人権を無視した元タレントや某テレビ局の経営陣、あるいは死人に鞭打つかの誹謗中傷を繰り返す某政党党首や部下の死に対して無感情な言動を放つ再選した某県知事等々の立ち振る舞いなど、挙げれば枚挙にいとまがありません。さらに、海外に目を移すと、つい最近返り咲いた某国の大統領などは、弱い者に対して血も涙もない政策を平然と大統領令に署名して実行に移すという、彼には人情の欠片さえ全く見出すことが出来ません。
ですから、世界を覆い尽くすが如くの目を覆いたくなるような人情味の無い醜い現実を目の当たりにすれば、舞台上の個々の人物のなんと人情味溢れる心根なのかと、劇中のようなそんな世の中に少しでも近づけることが出来れば争いごとも少なくなるのではと切に願わざるを得ませんでした。そのためには、私自身の身の回りからほんの少しでも良いので、他人への思いやりと真心を育んでゆかなければならないのではと改めて思いました。
では、現生の目を覆いたくなる嫌な話は脇に置いといて、再び視点を舞台上へと戻してみましょう。今回の観劇を観終わった際に感じた心地良い空気感は、その幕閉めの少し前にその理由があるのではと思いました。それは何かというと、終わり方が決して悲しい結末ではなく、定番中の定番とも言うべき終わり方で「四方八方ハッピーエンド」だったからなのではと考えたのです。ですから、ハラハラドキドキな展開は皆無でしたが、その反面に先が読める展開で安心して観ることが出来たということが、大きな要因かと思います。そんなことから、改めてこういったお決まりの結末の舞台もイイもんだなと思った次第です。つまりは、平凡な日常の中でひょっこりと顔を出した些細な出来事が、人生に彩を添えて、時には予期せぬ思いもかけない方向へと転がってゆく…、そんなほんの少しの驚きのある人生って、なんだか愛おしい感じになって来るんですよね。
ということで、今回の観劇は、多くを語る必要のない(既にここに至るまで多くを語ってきましたが…
さて、今回は歌舞伎のフィルターを通してどのように見せてくれるのかなぁ・・と。前もって、立川談志の噺を楽しんで/予習してからの観劇でした。
まず感じたことは、「そもそも、主役は明らかに(文七ではなく)左官の長兵衛なのに、また“元結”は取って付けたように最後にちょこっと出てくるだけで、筋立てに全く絡まないのに、なぜ“文七元結”なのかなぁ・・」と、「終わり方があまりにも素っ気なく/貧弱/手抜きになってしまってるような気が・・」、それから「併演の“楽しい歌舞伎”は、それなりに勉強になったのはいいが、本編の方の下げ〆に必要な“尺”を喰ってしまっていて残念・・」というのが大きなところ。
この大事な下げ〆を「金が出てきたからいいけれど、出たほうが不思議なんだよ。出なかったらどうするつもりだったのさぁ。に“あの金でチビチビやってたら駄目だった。これが“ここ一番の博打”だった。あれでぴちっと博打をやめられた“と長兵衛に言わせ・・、貧乏だと言ったって皆のいるところに裸でよく出てこれたなぁ。にはカミサンに“裸になって、人間がわかった”とも言わせて・・」と談志は括り/余談で締めていたが・・。
それから、金をやる。逡巡する・・、あれじゃ金はやれない。やるときぁスッとやる。演出はそうだが、娘をカタに手に入れた金をねぇ・・。(“金をやるのはすっとやるのが江戸っ子気質なんじゃぁ?”、“娘をカタに手に入れた金をやることがなかなかわからない。”、“しょうがないからやって、最後はバタバタ・・。”、“えらいところを通りがかったから、しょうがないからやっちゃった。”)というのもありで、これがほんとに/不思議とシックリとくる。
博打に負けて裸同然で帰ってきて、呼び出されて出かけるのにも女房の着物を着て・・、派手な夫婦喧嘩や文七とのやりとりとコミカルな笑いの一方で、お久の孝行心、佐野槌女主人の心意気、和泉屋清兵衛の粋なはからい、実直な文七などなど、ホロリの人情噺/落語を基にした脚本で、悪い人は誰も出てこない。それがもう、みんな、み~んな、いい人ばかりで・・。ほんと、現実の世界ではあり得ないことだろうがねぇ・・。
幕末から明治初期にかけての江戸で、田舎侍(薩摩/長州)が我が物顔で江戸を闊歩していることに反発して、江戸っ子の心意気を誇張して魅せるために作ったのでか、江戸っ子気質が行き過ぎて描写されてもいるような気がするものの、人間模様/関係の機微がテーマになっていて、よく考えているとリフレイン(音楽のそれで、英語のrefrainではない)することが多々あった、ほんとに。
もっとも“噺/話の世界”と“現実の世界”を一緒にしないという大前提の下ではあるが・・。
ところで“文七元結”は、ドタバタ喜劇みたいにしてしまうとちょっと違うのではと感じていたので、そういう意味でも今回は少しばかり抑えられていたようでよかった。
善い行いには良いことが、よろしくない行為には悪い事がという“因果応報”はぴったりこない。じゃあ“文七元結”は、“利他の精神”が充ちている演目なのか。娘も佐野槌のおかみも長兵衛も、みな“利他”で生きている。そう“利他”なのかといえば、そうでもない。
障害者福祉を問うた映画、大泉洋演じる筋ジストロフィー患者の主人公(「こんな夜更けにバナナかよ」-原作は実話)が発した「鹿野ボラ、ナメないで下さい。」が重なってしまう。(これは、“24時間交替で張り付いてくれるボランティアの支えがなければ生きていられない”にもかかわらず、わがまま言いたい放題で、ボランティアをこき使う・・正直なところ、自分では出来ないことを、ボランティアに口うるさくワガママばかりを言う主人公。そう感じてしまいがちで、正直あまり共感/感動出来ないことだけれども・・)。 ボラの彼らは“うんざり”しながらも・・、そこにあるのがまさに“利他”である。とすれば、文七になんの義理もない長兵衛は、このボラに近いのだとすれば“利他”なのかなぁ。
傲慢で不遜の極みの(と世間から見られていた)談志解釈に、真の“利他”を見るというのも面白いのかもしれないが・・、まったく違う気もする。
見ず知らずの人を助けたことが巡り巡って身内のところへ戻り、ハッピーエンド。“文七元結”からひしと伝わってきたのは“情けは人の為ならず”であった。
この噺には不自然な部分がとっても多い。真夜中にお久が一人で本所から吉原まで歩くのは不自然だし。見ず知らずの文七の身投げを止めるため、娘が自分を売って得た50両をやってしまう山場/くだりになくしたら“身投げ”するしかないような大金を、生きるか死ぬかの瀬戸際で腹をくくる、覚悟を決める、歌舞伎での“見得を切る”というあり方ですかねぇ、全体に流れているのは・・。それが出来た人情を持っていた長兵衛は左官屋でも大成してただろうし。
自殺の現場に居合わせたなら、何が何でも阻止したいのも人情だが、その50両を渡してしまったら、娘が遊郭で客を取らされることになる。自分だけならともかく、娘の一生を不幸にしてまで他人を助けるのが人情なのだろうか? それに、最後にお互いに見知らぬお久と文七が唐突に結ばれるし。(この時代はそんなものだったのかも知れないが・・)
よく考えると気になるのが、10両盗めば“打ち首”の時代に50両もの大金を、佐野槌の女将が返済を一年待ってやると言いながら・・、はなから1年間の猶予で返済は不可能だと承知でのことではないのか・・、と無粋な勘繰りも考えられるし。それから長兵衛は単純に、死のうとする文七に共感することは一切なく“ここでオレが金を出さないと、こいつは死ぬ”という、この関係に耐えられなかっただけのことだとも・・。そもそも、金をやってしまう理由すら、本当には語れないのではないか。吾妻橋の上で、たまたま身投げする奴に出逢ったのが、長兵衛の不幸だったという単純な考えも・・。
それとも、死のうとしている人間を前にして放っておくことなどできない。そして、いったん手放したものはそれが大金であっても再び自分のものすることなど恥ずかしくてできない。弱い者の味方だけども見栄っ張りという江戸っ子気質がこの噺のテーマなのかなぁ・・。
軽~く言ってしまえば、幼き日に常設小屋で何も考えずに、ただただ素直に楽しんだ“時代もの”と重なる/特に感激のない舞台だった気がする。そして、そのように素直に楽しんだが、時代のバックグラウンドを考えればいろんなことを込めた良い作品を選んだものだとも・・。
加えて、時代の背景が強制した“女人禁制”が、その功が/伝統が生んだ現代歌舞伎での女形の存在感/迫力/必然性の一端を垣間見たような気分になったのが、初めての経験で新鮮な感動でしたねぇ。ほんとにこれはよかった。
お芝居の方は、ザ時代劇の内容がとても心地よかったし、面白かったです。あと、川縁の舞台がとてもきれいで、見惚れました。
後半「人情噺 文七元結」短時間での舞台の変わりよう、素晴らしかったです
(ぶ)たい(舞台)はぼろ長屋。お兼が一人、立ったり座ったり所在ない。そこに下半身むき出しでみすぼらしい形(なり)の夫、長兵衛が帰ってくる。
(ん)?これはひょっとして、賭け事に負けて身ぐるみ剥ぎ取られたのか?案の定、そうだった。そしてお兼の落ち着かない原因は、17歳の娘、お久が帰ってこないことだった。
(し)る由もなし。お久は、一人で考えに考えて、吉原の遊女屋佐野槌へ、自分で自分の身を売りに行っていたのだから。
(ち)いさいとばかり思っていた娘が、家業をほったらかして博打や酒にうつつを抜かし、借財を増やす一方の父親と、それを咎めては喧嘩ばかりする母親を見るにつけ、心を痛め、二親の行く末を案じた果ての行動だった。なかなか出来ることではないが、思い切った手に出たものである。その後、心を入れ替え、五十両という大金を手にした長兵衛だったが、、、
(も)う少しで家にたどり着くというその途中の川縁で、身投げをしようとしている若者と出くわす。助けた上で身投げの訳を聞く長兵衛。今、まさに自分の懐には若者が必要とする五十両の大金がある。さあ、どうする、長兵衛!娘か若者か!二人を天秤にかけた末、命には代えられないと若者に五十両を投げつけるようにして走り去る長兵衛であった。しかし、
(つ)ま(妻)のお兼から、いつものように博打ですったんだろうと責め立てられ、ふてくされてふて寝を決め込む長兵衛。間に入ってオロオロするばかりの家長(いえおさ)。
(と)つぜん(突然)、そんなところに現れたのが、和泉屋の店主の清兵衛と長兵衛が助けた若者の文七だった。そして、清兵衛から事の成り行きを聞かされる。最後には清兵衛の
(い)き(粋)な計らいで、親孝行者のお久と、真面目な文七が夫婦になることが決まる。照れながらも、文七は、和泉屋から暖簾分けをしてもらった暁には、短く切って使いやすくした元結で商いをしていきたいと決意を述べた。
粋と言えば、今回もその存在の大きさを示してくださった佐野槌女主人、お駒役の山崎辰三郎さん。あの声といい、言い回しといい、何と言ってもあのどっしりとして動じない存在感が圧巻だ。そこにいるだけで、歌舞伎の粋を示しているようにも思える。これからもご健康で、末永くいろいろな役を演じて頂きたいと思う。地元徳島の宝人だ。徳島と藍住と両方で観させていただいて、心からそう思った。
「ありがとうございました。」
歌舞伎の立ち廻り、舞台の造り、音楽などすべてが楽しい雰囲気を作り上げていた。江戸っ子気質がこの人情噺にあらゆるところで表現されていて盛り上げていた。
観客を楽しませるためのさまざまな工夫、長い歴史を重ねながら今に至っている。日本を代表する伝統芸能だということが最初の解説でよくわかりました。劇団前進座の皆様に感謝感謝です。
又、次回を楽しみにしています。
(ぶ)たい(舞台)の裏側がどうなっているか、ご存じですか?
(ん)?知らない?わからない?見たことない?そりゃあ、そうですよね。
(し)ちゅえいしょん(場面)によって変化する舞台の背景より、そこで演じられている役者さんのセリフや動作に目が行き、舞台背景を凝視するなんてことはないですから。でも、その
(ち)ゃんす(チャンス)はあります。年6回公演のうちの運営担当サークルの時がその機会です。運営サークル担当時には、劇団員さん達の歓迎から送迎までの間に、いくつもの楽しい行事が見え隠れします。
(も)っと知りたい見たい舞台裏、と思ったそこのあなたは、まず、劇団員の方達と一緒に、荷物の運搬作業を手伝ってみましょう。
(つ)らいことも重たいこともありません。大きな荷物は劇団員の方達が全て運んでくださいます。私達は横で待つ間、今運ばれている物が舞台上でどの位置に設置されるんだろうと想像を巡らせていればいいのです。私達が運ぶものは、長いけど軽いものを人やものに当てないように前と後ろについて運んだり、小さいけれど少々重いものを左右について運んだりするだけです。
(と)らっく(トラック)一杯の荷物がすっかり片付き、何もなくなるのを見届けるのは壮観です。劇中で、自分が運んだ荷物がどの場所にどのように設置されているのかを探しだすだけでも、いつもの観劇より、余計に楽しめること間違いなしです。
(い)ちばん言わなければならないことが最後になりました。そうです、舞台裏を覗けるのがバックステージツアーというものです。劇団員さんの一人がその案内役をしてくださって、舞台装置や小道具の説明をしながら、舞台裏を回ります。そしてそして、そのツアーの前には、劇団員さんとの挨拶交流があります。ほんの間近で劇団員さんに会えるのです。運営担当サークルの時はメンバーを増やさないといけないのでしんどい、と思われている皆さん、そうではありません。自分たちが徳島という地元で、現在も将来も劇を見続けるために、仲間作りをしていく必要があるのです。運営担当サークルのメンバー同士をよく知り、仲良くなれるチャンスです。「運営サークルのマーチ」にあるように、新会員を増やすのには苦労がつきものです。でも、その苦労も、一緒にやっているという実感があり、苦労はやがて大きな喜びとなります。これはやったらわかります。どうか、運営担当サークルになったら、喜んで参加しましょう。そこにはたくさんの仲間の笑顔があります。一緒にやればこそ、クリア出来たときの喜びも大きく、その後の観劇がより一層、楽しめること間違いなしです。
一番最後になりましたが、劇団員の一人にインタビューもできます。私の妻は、一年前の佐藤B作さんとの出逢いで、ぎっくり腰を治して頂き、いまだに再発はしておりません。今回は有田佳代さんでした。とても優しい方で、ご自分もお母様と共に熊本市民劇場の一員であったことをお話くださり、とても楽しいひとときを過ごすことができました。
この劇の幕間も長かった分、長すぎるなーと思っていたが、幕間が長かった分、景色や背景の美しさが幕そのもので用意されていて、美しいことに気付いたりした。
ところで、彼の“まごごろ”は困った人と同じ苦しみを共有するところが“ステキ”で、あわや赤貧の中に自分自身も近いのに、自分の分は気にしない。比べてみることはしないのか?あー、面白くもあり人情というのはこの事で、生きるという事は、他人さんの人生もそっくり味わって…味わう必要がありますねー。
いつもとは違う栄養を身につめて帰宅させていただきました。ありがとうございました。

E-mailでのお問い合わせは、 鳴門市民劇場ホームページ
nrt-geki@mc.pikara.ne.jp
まで。