

■ 竹下恵子さんの熱演、加えて最後のクライマックスの場面で涙ぐむ自分がいました。戦後に生まれ空気のごとく自由があったことに感謝。
■ 天安門事件から30年以上も経つというのに、いまだに終わっていないという事実。そして真実は捻じ曲げられたままであるという事に衝撃を受けた。母親の悲痛な叫びを竹下恵子さん演じる「シウラム」が私達に訴えかけているようだった。映像と舞台が融合した演出は、臨場感があり、圧倒された。ラストシーンは自由を求めて命を落とした若者の叫び、悔しさ、無念さがダイレクトに伝わってきて、熱いものがこみ上げてきた。私達に出来る唯一の事はこの事件を決して忘れないという事であると思った。
■ 最愛の息子を天安門事件で失いながら、何も知らされず、何も分からないまま、そして弔ってやることも出来ないまま30年間悲しみ、苦しみ続け、あと数日の命となった時に決死の覚悟をして結構するという壮絶な生き様を描いた舞台。竹下恵子の熱演に大拍手!!自由にモノが言える日本に生まれて本当に良かったとつくづく思わされた。
■
自由を求めて民主化運動をなかった事にされたら、両親はたまったものではありません。国家はとても理不尽です。
親の立場になれば、どんなにか悲しく苦しかったことでしょう。怒りをぶつける方法もないのが現状です。でも、いつの世も若者が国を動かす原動力となります。
■ 竹下恵子さんの長セリフと演技力に圧倒されました。ほぼ、2人の会話だけなのに、最後まで見応えがあり、シウラムとアダイが強い意志を持ってなしとげようとする行動力にとても感動しました。
■ 中国のことはよく知らない。天安門事件、香港が中国になってしまったのは知っている。しかし、そこにいた人が何をしたのかは知らない。戻りの終盤に歌われる二曲も心に残っている。
■
竹下恵子さんの演技が迫力がありました。
本当のことを隠そうとする権力に憤りを覚えました。今も不都合な真実を隠そうとする権力者たちがいっぱいです。
■ 個々の思いが自由に表現でき、行動できることのありがたさを思い知らされました。大切にしたいです。また、竹下さんと林さんの演技も時には笑いもあって引き込まれながら観ました。最後の皆さんの力強い歌声がとっても感動的で素晴らしかったです。ありがとうございました。
■
主演お二人の出ずっぱりの熱演に凄いな~と感じると共に、30年前、私は何をしていたんだろう?大きな事件だったので名前は覚えているけれど、まったく何も知らなかったんだなぁ~と思い知らされました。
ちょっと、勉強してみようと思いました。
そして、最後の歌のクライマックスに近付くにつれて心がわしづかみされたような感触を受けました。歌で心を揺さぶられるというのはこういうことかと思いました。
ありがとうございました。
■ スパイ防止法が厳しすぎる中国、ほとんどの国にスパイ防止法はあります。日本にはまだスパイ防止法がありません。美しい国日本、美しい故郷鳴門を守るために、スパイ防止法を制定する必要があるのではと、この劇を観て改めてそう感じました。
■
「圧巻の フィナーレは、歌 翼、得て 遡れ!時間(とき) 天安門へ」
フィナーレの大合唱で、劇全体が浄化(昇華)された感、しきり也。
まずは、最初に舞台に登場した竹下景子さんの大きさに、びっくり。後で聞けば、小柄な体格だという。そんな感は全く受けない。かぶり付きのお陰か、林さんの首の滲む汗まで、よおく見える。(サークルに新会員を迎えた恩恵に浴す)
夫婦喧嘩の場面が、幾度も繰り返される。激昂する妻、忸怩たる自らの保守保身行為に猛反省の夫。しかし、突き詰めれば、息子への断ちがたい思いと妻への愛が底流にある。こんな苦しい話で終わるのかと思いきや、フィナーレの大合唱で救われる。
■
政治的圧政に対する天安門事件の悲劇を死ぬまで背負う親たちの苦悩と反抗を真に迫る演技で観せてくださいました。
死が迫る中、残された時間を「愛する息子が活き、そして散った証と弔いをする」ことを目標に力強く活ききった母親の姿に感動しました。
■
最初5月35日 え?と思いました。
1989年6月4日の天安門事件は今もこのような隠語のような言葉で語られているのかと。民主化を求めるデモに対して問答無用で武力で押さえつける。多数の死傷者を出し、その遺体の損傷の激しさゆえ、最期のお別れさえ許されない母親の怒り、苦しみ、悲しみ、自身の残り少ない命をかけて、ただあの場所で蝋燭を灯して弔いたい、母として愛する息子を理不尽に奪われた心からの叫びには、心がえぐられるようで涙が溢れてとまりません。遺族の方々にとっては何年、何十年たとうが忘れられるはずもなく苦しみぬいていきている、常に監視下に置かれながら、私にはとても耐えられない、観劇中何度そう思ったことか、
考えさせられることの多い舞台でした。全身全霊で演じられている役者の方々の迫力ある舞台に感動で一杯です。ありがとうございました、
■
1989年6月4日、中国天安門広場で民主化を訴える学生や人民が、政府の弾圧により亡くなった。ああだから、6月4日=5月35日なんですね。私は、2002年に観光で天安門広場に行きました。そこには赤い建物の天安門が静かに建っていました。広場の隣でご老人が太極拳でしょうか、ゆっくり体を動かしていました。空は青く高く、どこまでも無音の世界が広がり、美しい絵画のようでした。
でも、この広場でたくさんの人が尊い命を失ったんですよね。感無量です。
舞台の最後に魂の叫びともいえる歌声が強烈に胸を打ちました。愛した息子へのつきぬ想い、悔恨、そして自身の懺悔、いろんな感情がぐちゅぐちゅで、思わず私は最後に泣いていました。
素晴らしい舞台をありがとうございました。
■ 人として大切にしなくてはいけないこと、生き方を考えさせてくれる作品でした。
■ 竹下景子さんの声もお芝居も素晴らしく、圧巻でした。同じ母親として感情移入するのがつらく、特に後半は気持ちを切り離さなくては観ていられないほどでした。救いを得ることが難しい物語でしたが、観ることができて良かったです。
■ 強盗にはノリノリで加担しようとする若者が、「6月4日」には絶対に関わりたくない様子だったのが気味が悪くて怖いと思った。
■
実際にあった天安門事件で犠牲になった息子さんがどのようにして亡くなったのか、その真相を知りたいのに、できない母親の怒りが私には伝わってきました。主演の竹下景子さんいい演技をされていたと思います。
もう少し近くで見たかったです。
■
(5月35日)なんだか、不思議なタイトル。これは6月4日の天安門事件の日を指す隠語だそうだ。なぜ、5月35日と言い換えなければならなかったのか・・・。
(が)外出先から帰って来た一人の老婆、それがシウラム役の竹下景子さんだった。家の中をうろうろ歩き回り、落ち着かない様子。女優さんとは凄いものだ。当たり前だけど、もう老女になりきっている。
(つ)続いて帰って来たのは夫アダイ役の林次樹さん。少々ダミ声だ。人の良さそうな優しそうな旦那様だ。でも、彼に対する妻のシウラムの言葉は荒々しく、夫にいらだちを隠せない様子。どうしたのだろう。
(さん)散々夫の行動や言動をなじる妻に、夫はあきれながらも妻をなだめ、言い聞かせる。劇が進んでいく中で、息子の大切にしていたチェロを手放す時がきていた。そのもらい手に、自分の息子がどんなに優秀で優しい子であったかという自慢をやめない母シウラム。息子を心から愛し育んできたお母さんだったのだ。その愛する息子はもういない。国家権力に消し去られた。死に目に会えず、屍も未だに返ってきていない。なぜ、殺されたのか、どのように殺されたのか、何もわからず、悶々と過ごした30年。
(じゅう)重要な場面はあのシウラムがイスに縛りつけられたところ。アダイの弟に投げつける国家権力への怒り。自由に発言できない、自由に知りたいことを知り得ない、地団駄を踏みたくなる腹立たしさをアダイの弟に思いっきりぶつけていた。持って行きどころのない感情を吐き出す彼女の激しさに圧倒された。
(ご)合理のない不合理の世界。真相究明と犠牲者の名誉回復を求める遺族の声は、徹底的に封殺される。シウラムは余命三ヶ月を宣告されたのを機に、天安門に行き、息子のために弔いのローソクを立てるという誓いを立てた。夫と二人で密かに計画を練り、着実に準備を重ねる。絶対に自分たちの思いを遂げようと、夫のアダイは清掃員になる。しかし、シウラムの身体はどんどん病魔に犯され、目的を遂げようとするその日にはもう身体も動かず、意識も混濁した状態となる。そのため、夫のアダイは一人でその計画を実行しようと外に飛び出す。しかし・・・
(に)逃げない。どんなに迫害されても、その隙間をぬって考えられる限りの計画を練って自分たちの思いを遂げる、そのための身を削るような日々。それでも、その目的があるからこそ、生きてこられたのではないか。まさに竹下景子さん演じるシウラムとその夫アダイの人生そのものだった。
(ち)地球の今も平和な世界とは言いがたい。あちらこちらで理不尽な闘いが続いている。なんで人は戦う、争う、傷つけ合う!ただでさえ、自然の驚異があり、山火事、地震、大水害と世界のあちこちで起こっているというのに。人の手によってなぜ人を、人の居住地を破壊するのか!怒りではらわたが煮えかえる。
■
主演のお二人をはじめとする出演者のみなさんの演技、舞台装置の演出、そして、クライマックスの若者のたちの歌。
全てにおいて、「心に響かないもの」がひとつもなかった。
わたしにはこの春に大学生になった息子がいる。
作品中で、シウラムの息子は大学生になることなく死んだ。
奇しくも、天安門事件のことを知ったきっかけは、高校で世界史を学んでいた息子に教えてもらったことだった。
息子を失った母親の悲しみ、死に際に会えなかった悔しさ、死の本当の理由を明かすことのできない怒り。
何もかもが彼女の想いと重なり、終演までの間に幾度となく涙が流れ、クライマックスの劇場が割れんばかりの歌声に心が震えた。
市民劇場に入会して2年が経とうとしている。
毎年6作品中1作品は、生涯心に残る作品に出会っているが、2025年度は間違いなく「5月35日」だろう。
■ 天安門事件当時は、私はあまりニュースを見てなかったので詳しくないですが、他国のことですが、今からでも知っておかないといけないですね。
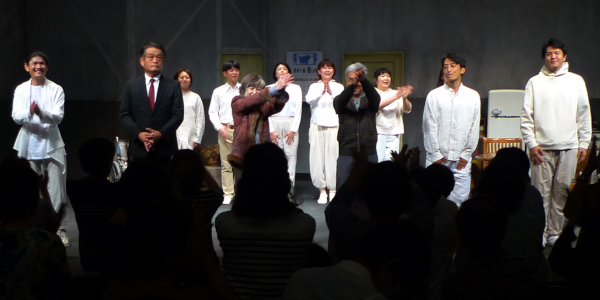
■
今回は、観ながら、そして観た後「私があの立場だったら…?」と自分を物語の中に投入してみる作業と「この作品が創られ、今私たちに提供されている意味」を考える作業を行ってみた。演劇を観る意義ってそういうところにあるんじゃないかな…と最近思っているからであり、この作品がその作業にピッタリだったせいもある。
最愛の人が理不尽な死を遂げた。その哀しみと悔しさを何十年も、自分が死ぬまで持ち続けることができるか?そしてそれを晴らすためにすべてをかなぐり捨てた行動に踏み切れるか?もちろん理不尽さの加減にも依るだろうが(シウラムの場合はそれは想像を絶するほどに大きな理不尽さだった)多分、私には、できない。他の人よりはひとつのことに引きづられ長く苦しむタイプではあるものの、きっと長い年月の中では、なんとか“折り合い”をつけて生きていくような気がする。そう結論したあと、なんて私は弱い人間!と気づき、ちょっとがっかり。これは“アダイとシウラム”に自分を投影してみた結果。一方、舞台では直接は描かれていなかったが“ジッジ”たち、声を上げ立ち上がり、命をも厭わず戦った若者たちについてはどうだろう。人生の中で、叫びたい主張があり訴えたい正義があり仲間とともに…というパッションが湧き上がってくる場面はあるかもしれない。でもどこまで激しい行動をとるか?最後のところでは自分の行為によって影響が及ぶであろう親兄弟のことも考えて危険をはらむことには怯むような気がする。再び、なんて私は弱い人間!である。ただやはり、彼らが置かれていた(おかれている)過酷な(国の)状況は今の私たちの環境とはかけ離れすぎてていてなかなか「もし自分だったら」を具体的に想像ができないところもあるだろう。しかし…である。「あの国は大変だ。私たちの国はそうではなくて、良かった」ではなくて、ああまで極端ではなくても、私たちの身の回りにだって、表現の自由や平和を脅かしかねないなにかしらのリスクは常に潜んでいる。常にアンテナを張り、正しい判断をし、必要なときには声を上げる勇気をもつように…そんなことを教えてくれたのではないかと思った。そういうところにこの劇を観た意義があると思った。
1989年の「天安門事件」はすでにはるか遠いことのような印象だが、2019年の香港民主化デモは記憶に新しい。本作品が香港で上演されたのが(偶然?必然?)2019年、そしてデモが鎮圧され「香港国家安全維持法」が制定されてからは、この作品は香港で上演されることは二度とないときく。もちろん劇が上演できないということだけではなく、自由な言論や行動をとることが一層厳しくなったということ。舞台上で最後に力強く歌われた歌は2019年の香港民主化運動の際のテーマソングということを知り、1989年と2019年を繋ぐ見事な構成であったことに唸らされたが、二度の、またその間何年にもわたる、自由を求める運動にもかかわらず、余計に制圧が厳しくなっているという事態を目の当たりにしたようで、高らかな歌声とは裏腹に、ものすごく悲しい思いが胸に迫って来て苦しくなった。
だから…。この話は、決して「過去のこと」ではないし「どこか遠い国のこと」でもない。今起こっていることであり、身近にもあるかもしれないことである。怖さを正しく認識するということがこの作品を観たまたひとつの意義のひとつだった。
最後に。こんな重いテーマを携えながら、どこにでもあるような老夫婦の(ときにクスっと笑えるような)会話の場面、最後が近い夫婦間の愛情に胸が熱くなる場面、天安門事件の生々しさが映像で伝わってくる激烈な場面、息子を思うあまりのシウラムの狂気のような慟哭に胸が苦しくなる場面など…みごとに緩急がつけられた構成・演出、そして林さんと竹下さんはじめ役者さんたちの演技はとても素晴らしかった。
■ 他国の出来事であっても、子を思う親の心は同じもの。絶望や無念が切々と伝わって来る劇でした。
■ 最愛の一人息子を納得できない事件で亡くしてしまった悲しみはいかばかりかと…想像を絶するものがあったと思います。 また、余命わずかと知り、危険なことと知りながら息子の弔いをしようとする姿はすごくもあり悲しくもありました。
■
最初から皆が少しづつ狂気をはらんでいて、アンバランスで不穏で低いトーンがずっと流れていて。明るい照明も高いトーンも、あの2回だけだったしこれももう怖かった。最初のシウラムの冷たい冷静さやアダイの子供っぽさからして不穏だったわあ。
「最愛の息子を奪われた」ことに加えて、どのように死んだのかも知らされない、遺体も返されない(アダイは見た)、語ることも許されない…何重にも何重にも奪われていることからしみ湧き出てくる怒りというか恨みというか…最初は目に見える狂乱なんだけどその後は静かに重くて固くて冷たいものに変わって行ったものというか。うぅぅ。胃が痛い。
アペン・アダイ兄弟の血のつながりにシウラムがイライラするのもわかるなあ。とか。
弔うって、それぞれの人の中で死者への最後の始末をつけることなのだなあ。のちに生きる人にとってとても大事なことなのだなあと思いました。
決行の日、もう座っていることもやっとで意識も混濁していて、アダイが出ていった後、独白しながらどんどん意識がクリアになって立ち上がった時に、「ああ、シウラム死んだんだ」と涙がぶわわと出て来て。よかったのか残念なのか分からないけど。その後客席から息子?が、若者が出てきて高らかに強く歌うところは感動もあったけれども怖くって。きっと日本ではわかりえない、国家と戦うという理不尽に立ち向かう、平和脳では理解しえないものを感じました。
息子への愛情も、私たちは過剰な気がするけど、中国の人ならさもありなん?
■
「計り知れない悲しみや絶望や怒り等が、ひしひしと伝わって来る見応えのある劇だった。
そんな風に思い、100%解ったような顔をしているけれど、本当は「うわべ」だけしか解ってないと思う。
風化させてはいけないと思う出来事もたくさんあるけれど、過去には戻ることもまた変えることも出来ないので、自分としては、そう言う出来事や事件についてあまり深く考えることがない。その点、未来は自分の力で変えることもできるし、そんな可能性をいっぱい秘めている。未来の方を重視したい。
■
いつもならあれやこれやと思い浮かべては構想を練る「感想文」の原案が、意に反して今回は全く思い浮かばず、筆が一向に動き出しません。
そこで、まずはその理由は何かと考えを巡らすと、今回の観劇(5月35日)が、私の琴線に全く触れなかったことが、第一の理由かなと思い至りました。さらに、今回の劇中で表現された老夫婦の日常と劇の第一義的な背景となった「天安門事件」との繋がりを、私なりに紐解いてみました。しかし、考えれば考えるほど、両者の繋がりが見えて来ず、むしろ泥沼に陥ってゆくばかりでした。また、今回の劇の解説には、「ひとり息子の天安門事件での不可解な死を抱えながら何もせずに生きてきた老夫婦が人生の終焉で、息子の死に向き合うために事件の起きた天安門広場で息子を弔うこと」と記されていました。ですが、私にはその二つの事件の間には、非常に大きな隔たりがあるように思えてきてならないのです。というのも、「天安門事件」が国家を揺るがす大事件で、その広場での市民や学生に対する軍による武力での鎮圧の映像が流れて世界的にも大きな衝撃を与えたのは、広く知れ渡っていることです。一方で、市井の民である老夫婦のひとり息子がその天安門事件での軍の武力行使に巻き込まれて命を落としたというのも、その事件の大小は置いとくとしても、人の死という一つの事件です。もちろん、人の命の尊さや重みは何物にも代えがたいものではあります。ですが、今回の劇中で表現されたその国家を揺るがす大事件と一個人の死との間には、どう考えても私の中では直接的には繋がりきれないのです。なんというか、題材として「天安門事件」を取り上げて、それを「一個人の死」と結び付けるという脚本上のミスマッチというか、両者を繋げて関連性の高い物語を構築することに非常に無理があったように思えてならないのです。その為かどうかは定かではありませんが、舞台の幕開けから終わりまでの間を通して、今回の観劇での主張(主題)が明確になっていないような違和感を抱かざるを得ませんでした。ですから、私としては舞台上での演技に引き込まれることも皆無で、それ故に単調に時間だけが過ぎてゆき、時折大声を張り上げる役者の演技にうんざりしつつ、正直言って今回ほど何も感性を揺さぶられることが無かったのは、観劇に足を運びだしてから初めての経験です。そして、そんな状況下でしたので、不本意にも私は眠りに誘引され、時折フッと我に返ったように舞台上を見ると、いつの間にか情景は先へと進んでおり、当該劇の全容が分からないままに過ぎ去っていました。ということで、今回の感想文のネタが全く思い浮かばず、悶々として時が過ぎるのみでした。
そんな中で、舞台公演の情景を思い返しながら、今回の観劇のネタ、いわば主題(テーマ)は何だったのかと今一度改めて考えると、舞台の終盤で「母親を迎えに来た若者の霊の群れ」の中で演じられた「自由」が、本観劇の「主題」なのではないかとの結論に至りました。
それでは、「自由」とは何なのか?また、この「自由」との言葉の響きから、おそらく多くの方々は、それぞれ独自のイメージを抱くことかと思います。そこで、本観劇から得た「自由」という言葉に対する私なりの捉え方について、ご紹介したいと思います。
まずは、世界地図を開いて、我が日本を中心として、その左に位置する大国を見てみましょう。これは言うまでもありませんが、本劇での題材として用いられた「天安門事件」が起こったかの国に目を向けると、そこには私の考えるところでの「自由」というものは存在しないように思います。もちろん、そのような国であっても人々の日常は途切れなく日々営われてゆくわけですから、「それなりの自由」が存在するのは、言うまでもありません。とはいうものの、さらに恐ろしいことに、かの国では人々の「自由」が監視社会の下で益々狭まれてゆく様を見るにつけ、何とも言えない恐怖感を抱くのは私だけではないと思います。つまりは、現主席による独裁政治の色合いをさらに強固にと色濃くしてゆく現状を目の当たりにすると、かの国の国民の行く末を憂うるばかりです。
それでは、次に地図上での視線を右に移して、一方の「自由の国」での民主主義国家の代表格である大国に目を向けてみると、かつての「民主主義国家」の姿が徐々に崩れ始めている危機感を覚えずにはいられません。かの大国では、大統領に再選された人物の政権下で扇動にも似た「民主主義の破壊」が進んでいるように見受けられます。一例を挙げると、名門大学での「留学生受け入れ資格の取り消し」や「助成金の一部凍結」等に見られる政権圧力による「民主主義の破壊」です。彼の第一次政権での振舞から第二次政権での今回の暴挙は、ある程度予想可能であったかもしれません。しかし、これ程にも表現や学問の自由が奪われると、それを元の状態に回復させるのには、損なった時の何倍もの労力が必要になるのは火を見るよりも明らかです。ですから、表現や学問、はたまた言論や報道等の自由を失うことは、「民主主義の後退」に他ならず、最終的には民主主義そのものが破壊尽くされ「不自由」な「非民主主義国家」へと、民主主義の象徴とも言うべき大国が「独裁国家」へと変貌してゆく危機感を強く抱かずにはおられません。
さて、他国のみならず、私自身の足元である我が国での「自由」について、少し述べたいと思います。
先の二つの大国の「自由」に比べると、我々の国での「自由」は、多少は保たれているかと思います。ですが、よくよく「自由」というものを考えてゆくと、いわゆる「勝手気ままな自由」では互いの衝突が避けられず、そこには何某らの「ルール(≒法律)」が必要なのは言うまでもありません。そうすると、個々人での「勝手気ままな自由」は得ることは出来ず、そこには各々にとっての「不自由」が存在することになります。こんなことを考えていると、やや哲学的な押し問答になってきて、一向に先が見えません。ということは、我々の思い描いている「自由」というのは、「ある一定の規範内での自由」であって、それは「不自由と隣り合わせとも言うべきもの」かも知れません。いやいや「隣り合わせ」ではなく「表裏一体」といった方が、より適切かなと思います。ということで、現代社会で生きてゆく上では、「何らかの制限(制約)を受けての自由」なのでしょうね。
ただ、ここ最近の世の中の流れ、特に先日の選挙での各党が掲げていた公約や主張を見聞きするにつれ、この国の「自由」がステルス的に浸食を受けて変質してしまわないかと、個人的には非常に気になっています。というのも、一部の政党の公約等の中に「排外・排他主義的要素」が見え隠れするからです。それらは、特に社会的に立場の弱い人々をターゲットにして、国民の中の不満層の矛先をそこへ向けて己が党への票田を囲い込みたい思惑があからさまな感じだからです。そして、差別を助長・正当化し、ひいてはそれら政党を支持している人々からも「自由を奪うもの」へと変容しかねない危うさを孕んでいると私は思っています。しかもSNS等上では、これらの排外・排他主義をあたかも正当化するがごときの投稿が後を絶ちません。ですから、個人的には「○〇ファースト」といった一見すると聞き心地の良い言説には、印象操作の匂いを強く感じ、安易に取り込まれないようにしなければとも思っています。そうでないと、今までの「空気のように自然と手にしていた自由」が、あたかも「いつの間にか手錠をかけられて可動域を狭められた自由」となった息苦しい時代へと移り変わってしまったあとでは、後戻りは非常に困難な現実となると思うからなのです。
ところで、今回の観劇で一番気になった人物について述べて、私の感想文を締めくくりたいと思います。その人物とは、老夫婦を監視していた「秘密警察」の男性です。この人物は、政府の命令を受けて「秘密警察」の仕事に従事していたのでしょうが、彼の心情は果たして「自由」だったのか否か、そこがとても気になりました。幼少期から特別な教育を受けていたなら「洗脳状態」に陥って、政府の命令に何らかの疑問を持つことなどは微塵もないと思います。ですが、青年期あるいは成人してから「秘密警察」に入隊したとしたら、果たして彼は政府の命令に疑念も抱かずに心底信じていたのか、私には疑問しか湧きません。これはあくまでも私の勝手な想像ですが、政府の命令に従わなければ自身の命のみならず家族等にも危害が及ぶ恐れがあるという恐怖心から服従するしかなかったのではないかと思います。それで、そんなことを考えると、彼の心は「不自由」な状態に置かれ、彼の心の内では「自由を欲する気持ち」と「不自由な状態があたりまえという諦念の気持ち」との間での激しい葛藤があったのではないかと想像するのです。そんな彼の心情を思うと、国家による個人の「心の自由」の領域を侵すことは、決してあってはならないものと、改めて思いました。
■ 『記憶する』ということを、人間は大切にするのだと感じました。30年経っても忘れられない罪悪感、いろんな気持ちが交錯する。 悪名高い天安門だが、『犠牲になる若者』という人柱が近代国家には必要なのか?どの国をみてもある物語のような気もしました。
■
天安門広場での事、36年にもなるんですね。
細かいことは忘れていましたが、あの時の衝撃的な映像は忘れることはできません。後世に伝えるべき事だと改めて思いました。
■
場面の変わらない会話劇なのに退屈せず観られるのは脚本と演者がいいからですね。
次のも会話劇っぽいので楽しみです。
■
フィナーレの若い人達の革命歌に触発され半世紀以上前に仲間たちと歌った学生インターナショナルを帰りの車の中で口ずさんでいました。
あの頃は親の気持ちなんか考えもしなかったなー
■
夫婦は、それぞれ持病を持ちながら日々をイライラ暮らしていた。一人息子の死は、天安門事件のせいだとも考えられ、思い出す度に、早く言えば、夫婦げんかになった。ある日、夫や妻を家庭内暴力(手足を縛り、口を覆い、椅子に縛り)をした。原因は天安門事件において、息子死亡の原因が?で不可解なままだったという理由に問題があるのだけれとも…弔いをすることができないままだっただろうか…
夫婦が互いに慰め合わねば、自然にこういう形態に陥ると思われた。
我々に何を教えてくれているのであろうか…
■ すばらしい演技でしたね。30年前の天安門での不自然なひとり息子の死、その親たちのはかりしれない苦悩、その息子と向き合い追悼しようと思う一市民の願いも「真っ当でない国家」の前では、かなわない。でも二人の願いは、もう一つの世界で感ずることができ、わかり合える世界があると涙が止まりませんでした。そういう世界があることを見させてもらいました。
